感染症及び寄生虫症②
では、ここから各論について学んでいきます。
今回は腸管感染症についてです。
詳細な病名に行く前に、少しだけ食中毒について学んでおきます。
食中毒は細菌・ウイルス・原虫によるものにわかれます。
その中でも細菌性の食中毒は主に2種類あり、感染型と毒素型に分かれます。
細菌感染型の特徴
腸管内で菌が増殖し、菌により産生されたサイトカインにより、腸管粘膜が障害されることにより食中毒が引き起こされるものをいいます。
- 腸炎ビブリオ(A05.3)
- サルモネラ(A02.0)
- 腸管病原性大腸菌(A04.0)
- カンピロバクター(A04.5)
- クロストリジウム・ディフィシル(A04.7)
などがあります。
細菌毒素型の特徴
食品内で増殖した菌により産生されたエンテロトキシンなどを経口摂取し、食中毒が引き起こされるものをいいます。
- 毒素原性大腸菌(A04.1)
- 腸管出血性大腸菌(A04.3)
- 黄色ブドウ球菌(A05.0)
- ボツリヌス菌(A05.1)
- ウェルシュ菌(A05.2)
などがあります。

毒素型と比べて感染型は体内で菌を産生するため、潜伏期間が長くなり、症状も重くなる傾向があるようです。
では、病名にいきたいと思います。
コレラ –Cholera(A00)
特徴は
日本では輸入感染症がほとんどで、三類感染症に指定されています。
感染者の便で汚染された水を介した経口(糞口)感染で感染します。
コレラ菌は
コンマ状で1本の鞭毛を有するグラム陰性桿菌であり、ビブリオ科ビブリオ属に所属しています。
症状としては
コレラ毒素というものを産生し、それにより米のとぎ汁のような下痢になります。
この下痢により、脱水をきたし、コレラ様顔貌というものをきたします。
潜伏期間は、24〜48時間になります。

ちなみに、コレラ菌を発見したのは、ドイツの医師である、ロベルト・コッホ(1843年-1910年)になります。他にも結核菌を発見し、1905年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています。
治療は
- 脱水の改善
- アシドーシスの是正
- K(カリウム)の補充
- テトラサイクリン、カナマイシンなどの薬剤投与
が主な治療のようです。
腸チフス及び、パラチフス –typhoid and paratyphoid fever(A01)
特徴は
東南アジア旅行者の輸入感染症例が多く、省庁に特異的病変を伴います。
また、ヒトだけの病気です。
チフス菌及び、パラチフスA菌は
コレラ菌と似ておりに、三類感染症に指定されています。
また、鞭毛を有するグラム陰性桿菌で経口感染という点も同じです。
こちらは、サルモレラ属に所属しています。
症状としては
悪寒を伴う高熱とともに、徐脈・脾腫・バラ疹が三大特徴となります。
潜伏期間は、10〜14日になります。

コレラ菌に比べて、潜伏期間がとても長いんですね。
治療は
ST合剤や、ニューキノロン系の薬剤投与になります。
その他のサルモネラ感染症 -Other salmonella infection(A02)
特徴は
腸チフス、パラチフス菌以外のサルモネラ属による経口感染症を指します。
こちらは、ヒトだけでなく動物にも感染します。
子どもに多く、ミドリガメ等からの感染が多い。
他にもネズミ、鶏、卵、貝類などから経口感染します。
細菌性赤痢 –Shigellosis(A03)
特徴は
衛生状態の悪い地方に多発する、大腸の急性炎症性疾患になります。
三類感染症に指定されています。
赤痢菌は
真っ直ぐなグラム陰性桿菌です。

発見したのは、日本の滋賀 潔(1871年-1957年)です。同じ日本人として尊敬します。
症状としては
悪寒、発熱、腹痛で
潜伏期間は1〜3日になります。
治療は
ニューキノロン系が第一選択になりますが、多剤耐性菌も多いため注意が必要のようです。
細菌性食中毒 -Bacterial-food-poisoning(A05)
他の細菌性食中毒として、下記のようなものがあります。
黄色ブドウ球菌による食中毒(A05.0)
毒素型の菌。
手指などの傷口からブドウ球菌が食品中で増殖し、産生された毒素により発症する。
腹痛、嘔吐、水様性の下痢をおこす。
黄色ブドウ球菌自体は熱に弱い。
ボツリヌス菌による食中毒(A05.1)
悪心、嘔吐、めまいが主な症状です。神経系の毒素を産生するため、運動麻痺、呼吸筋麻痺を引き起こします。
新鮮な食べ物では起こらず、不完全な加工をされた保存食でみられることが多いようです。
ウェルシュ菌による食中毒(A05.2)
毒素型の菌。
土壌中や動物の腸管内に分布しているクロストリジウム属の菌。
腸炎ビブリオ菌による食中毒(A05.3)
感染型の菌。
好塩性の菌のため、夏に海産物や魚介類を介して感染する。
腹痛、嘔吐、発熱、水様性下痢、粘血便などがおこる。
アメーバ症 -Amoebiasis(A06)
特徴としては
エントアメーバ・ヒストリティカによる経口感染によるもので細菌感染症ではなく、原虫感染症。
熱帯地方の衛生状態の悪い地域に多く、大腸粘膜に壊死性の病変を作ります。
亜急性、慢性の経過を辿ります。
五類感染症に指定されています。
治療としては
第一選択薬として、メトロニダゾールが選ばれます。
ウイルス性下痢症 -Viral diarrhea(A08)
特徴としては
ウイルスによっておこる急性腸管感染症で主に冬に流行します。
乳幼児にみられる下痢を総称して乳児下痢症と呼び、ロタウイルス(A08.0)がほとんどを占めます。
他にはノロウイルス(A08.1)、エコーウイルス、ポリオウイルスなどがあります。
治療としては
基本的には食事療法と輸液になるようです。

ざっと腸管感染症について学んでみたので、今回はこのへんにします。
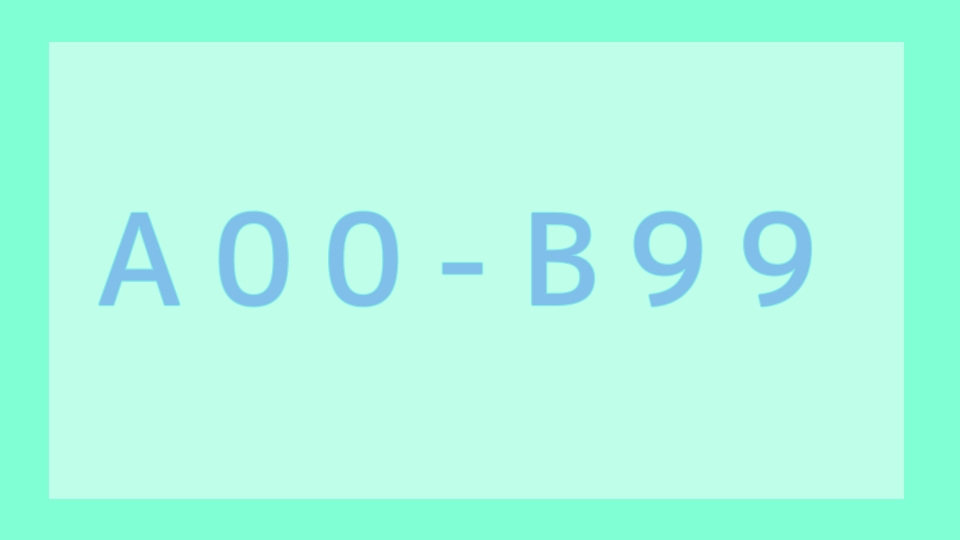
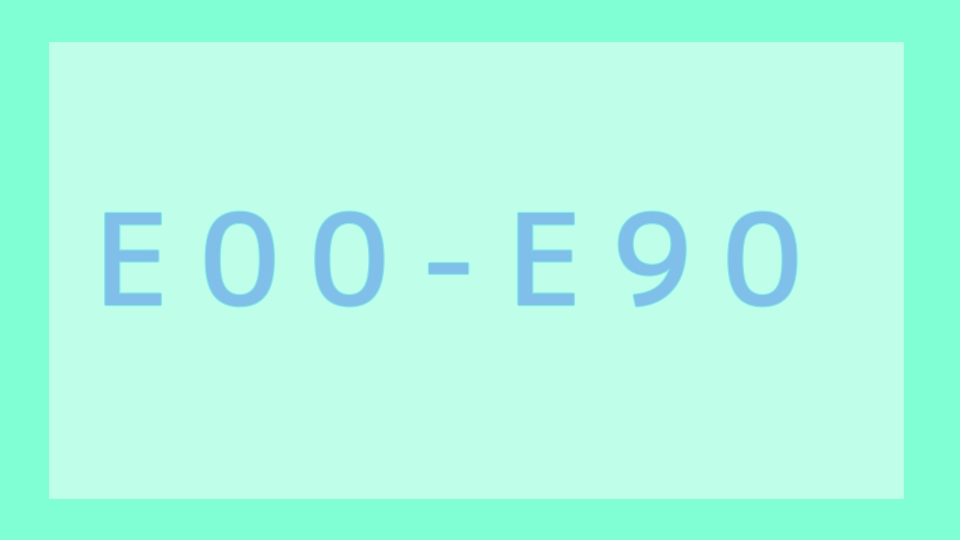
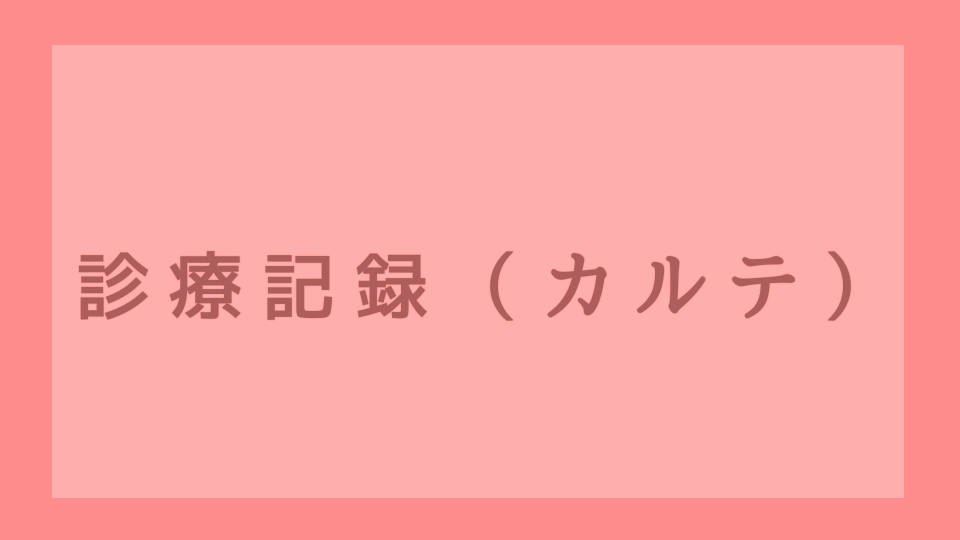
コメント