この記事は診療情報管理士のテキストやWeb等で検索し学んだことを自分なりに噛み砕いて記載しているので、間違いや不備等があるかもしれません。ご了承ください。
感染症及び寄生虫症①
こちらでは、感染症及び寄生虫症について学んでいこうと思います。
ICD-10のコードで言うと
- A00–B99
にあたります。
Aコード及びBコード病名の中分類は
- 腸管感染症(A00-A09)
- 結核(A15-A19)
- 人畜共通細菌性疾患(A20-A28)
- その他の細菌性疾患(A30-A49)
- 主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64)
- その他のスピロヘータ疾患(A65-A69)
- クラミジアによるその他の疾患(A75-A79)
- リケッチア症(A75-A79)
- 中枢神経系のウイルス感染症(A80-A89)
- 節足動物媒介ウイルス熱及びウイルス性出血熱(A90-A99)
- 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症(B00-B09)
- ウイルス肝炎(B15-B19)
- ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20-B24)
- その他のウイルス疾患(B25-B34)
- 真菌症(B35-B49)
- 原虫疾患(B50-B64)
- 蠕虫症(B65-B83)
- シラミ症、ダニ症及びその他の動物寄生症(B85-B89)
- 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症(B90-B94)
- 細菌、ウイルス及びその他の病原体(B95-B97)
- その他の感染症(B99)
となっています。

なこあ
順番に法則性を見出せないので、覚えれる気がしません。
言葉の定義
病名を学んでいく前に、感染症の基礎について理解しておきます。
感染とは?
感染とは、微生物がヒトの体内に侵入するとともに、組織に定着して増殖が可能になった状態をいいます。

なこあ
侵入しただけで増殖しなかったものに関しては、感染とは言わないみたいですね。
病原微生物の種類
病原微生物は何種類かに分かれています。
それぞれあげてみます。
- 原虫:最も単純で原始的な微生物。単一の真核細胞を持つ。
- 真菌類:カビや酵母などのような生活形態をもった真核生物核酸が核膜に包まれた核を持つ細胞(真核細胞)からなる生物。(例)ヒト、動物、植物。
- ウイルス:一番小さな病原微生物。核酸しか持たず、DNAウイルスとRNAウイルスに分けられる。
- スピロヘータ:細長いらせん状の形態を取る。グラム陰性桿菌。
- クラミジア、リケッチア:細菌の一種だが、細菌より小さく生きた細胞の中でのみ増殖する。
- マイコプラズマ:細菌の一種で、一番小さく、細胞壁を持たない。

なこあ
細菌とウイルスの大きな違いは、動物の細胞外で増殖ができるかどうからしいです。細菌は増殖が可能でウイルスは不可能です。
感染経路
病原微生物はその種類によって、感染経路が異なります。
- 経口感染
- 接触感染・経皮感染
- 飛沫感染
- 空気感染
- 媒介動物による感染
などがあります。

なこあ
麻疹・水痘・結核などが流行りだすと騒がれる理由は、空気感染だからです。
検査所見・診断方法
感染が起きると、血液検査で白血球の増加が起こります。
一般的には
- 細菌感染症:好中球が増加する。核の左方移動が起こる。
- ウイルス感染症:白血球の増加は少なく、リンパ球が増加する。
- 寄生虫症:好酸球が増加する。
が起こります。
他にも血清学的にはCRPが増加し、生化学的には、蛋白質の消費により、低蛋白質症・アルブミンの減少・グロブリンの増加・血中尿素窒素の増加が見られます。
感染症の診断には
- 塗抹標本:光学顕微鏡を用いて、ガラス板上に塗布された標本を観察する
- グラム染色
- チール・ネルゼン染色
- 蛍光抗体法
- 細菌培養:菌を培地で育てて起炎菌を特定する
などがあります。
血清学的診断として、補体結合反応やγグログリン分画の抗体反応を見ることもあります。

なこあ
いずれにせよ、大事になってくるのは病原微生物を検出し、特定することです。
長くなってしまったので、病名については次回以降にしたいと思います。
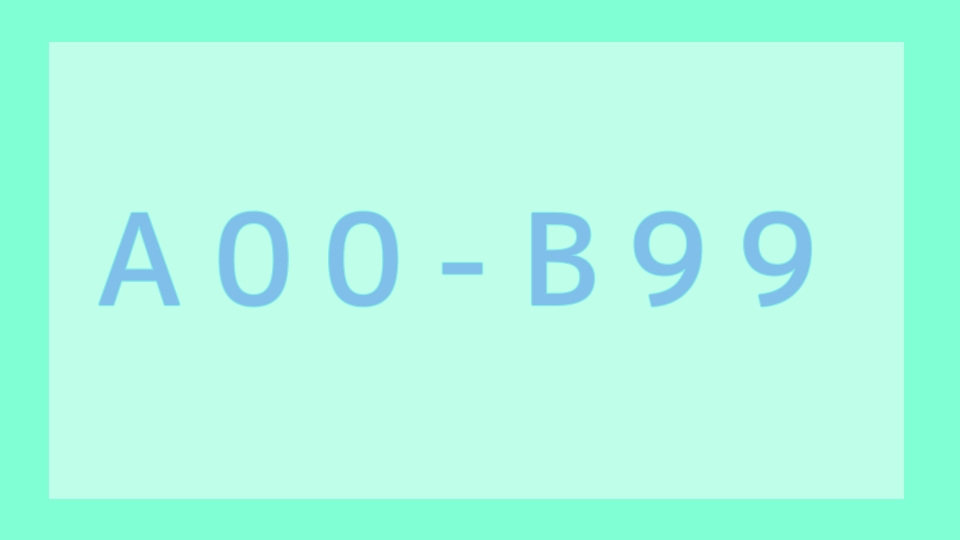
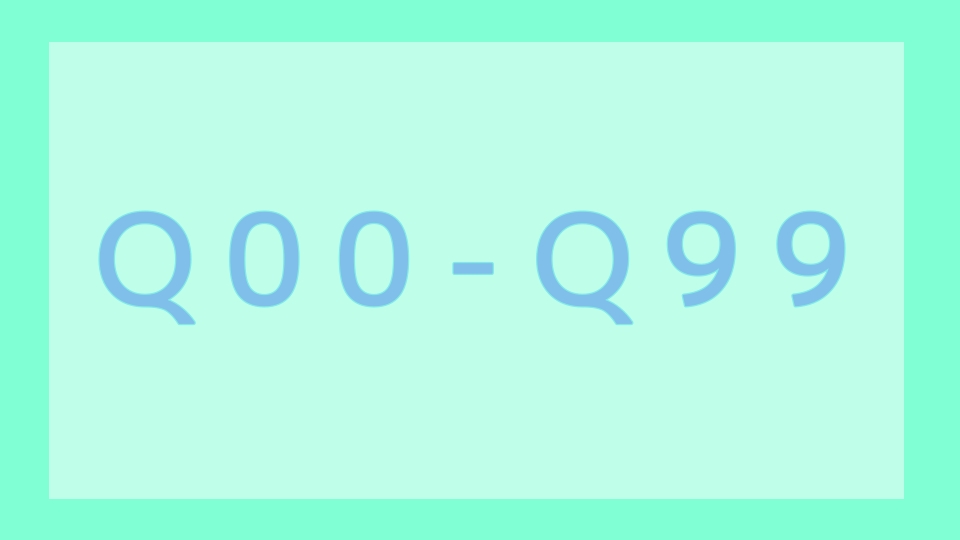
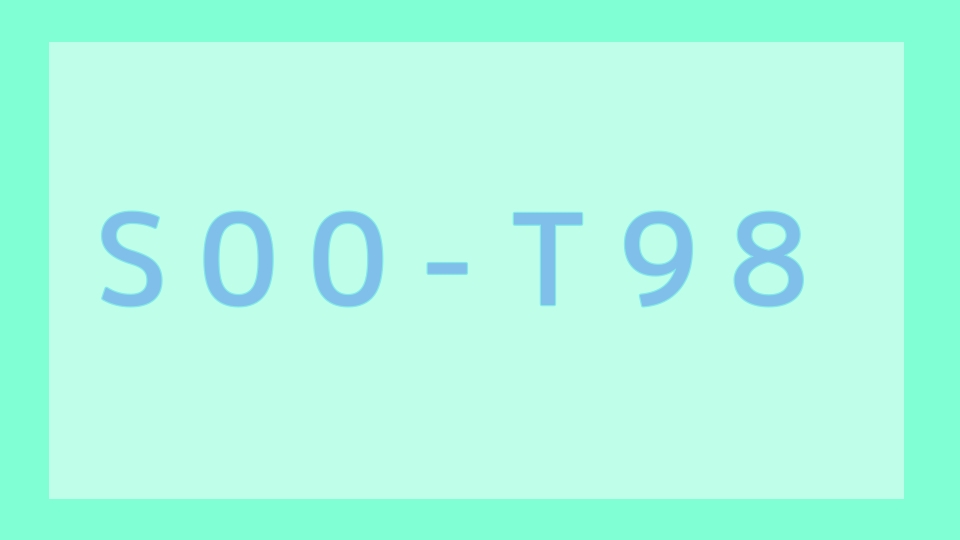
コメント